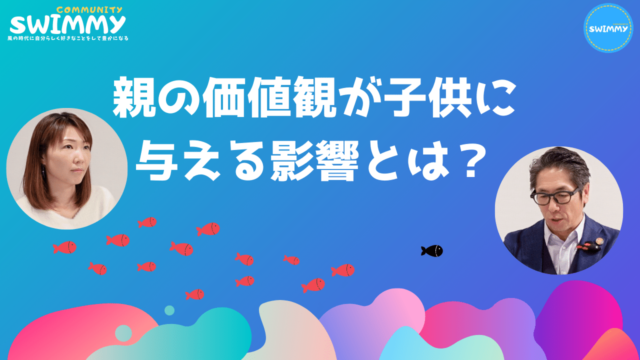こんにちは!swimmyコミュニティの間実夏(はざまみか)です。
Swimmyコミュニティは、好きなことや得意なことを活かして、社会貢献をしながら自分らしい生き方を実現させるための風の時代の学べる&繋がるコミュニティです。
前回のお話に引き続き、今回は
自己肯定感は親の影響が大きいのか??
というお話です。
動画で見る方はこちら
前回のお話を読む方はこちら↓↓
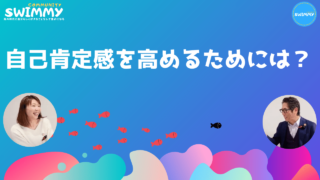
自己肯定感に親がどのように影響しているのか?
人は自分で意思決定したり、自分の価値観で生きています。
自分の価値観って、自分自身で作られていると思いますよね。
・・・・・・・・
実はそれ、大間違いなのです。
え???
でも、他人は然り、親や兄弟とも違う価値観だし、あまり似てないし…
どういう事なのでしょうか。
それは価値観が似てる似てないではなく
影響を受けているかどうかなのです。
そう言われると影響を受けているかもしれないな…と思いますよね。
価値観は100%親の影響です。
自分が産まれて親の庇護を受けて生きていますが
その間に親は子供に色々なことを言います。
「あれした方が良いと、これした方が良いよ」
大人も子供も顕在意識と潜在意識の割合は変わらないのです。
- 顕在意識(意識)
- 潜在意識(無意識)
大人は大した事を考えていて
子供は大した事を考えていない
というのは大きな間違いです。
親が子供に対して『出来る、出来ない』と言ったことは、
良くも悪くも、ずっと子供に刷り込まれていきます。
コミュニケーションを取らないと人はどうなるのか?
少し話が逸れますが、
昔このような実験が行われたことがありました。
子供がコミュニケーションやスキンシップを取らず、周りの関心を得られずに生きて行くと、どうなるのか??
「神聖ローマ帝国の皇帝フリードリッヒ二世(1194~1250)は、人類の言語の起源を確かめたいと思って、一つの実験を行った。人間の言葉をいっさい聞かずに育った子は、人類の根元語を話すに違いない、と思ったから、皇帝は生まれたばかりで捨てられた赤ちゃんを何人か選んで、保母や看護婦に養育させることにし、そのとき赤ちゃんに話しかけたり、あやしたり、機嫌をとったり、愛撫したりしては絶対にいけないと厳命した。入浴や食事など生命維持に必要なことはもちろん許したが、人間的接触を禁じたのである。
この実験の結果は出なかった。なぜなら、実験に使われた赤ちゃんたちがあまり大きくならないうちに全員死んでしまったからである。愛情や人間的出会いがないと、人間は生きることができないのである」
引用元:慶應義塾大学出版会 https://www.keio-up.co.jp/kup/kyouiku/zuihitsu/z201507.html
この時、人はコミュニケーションを取らないと死んでしまうという結果が出ているのです。

つまり、人はコミュニケーションやスキンシップという『関わり方』が重要なのです。
自己肯定感が低い本当の理由は?
自己肯定感は
I am OK(私はこれで良いんだ)
と自分を承認することです。
しかし
『自分を認めることが難しい』
と前回の記事でもお話をしましたが、何故なのか??
それは
自分がOKと思っていない事を親が言うことが多いから

例えば小さい子供はヤンチャなので、ついつい
「これをやったら危ないよ、いけないよ」
と思わず先回りして声を掛けてしまいますよね。
3歳〜7歳くらいは危険察知能力が未発達なこともあり、どうしてもこのような声掛けが多くなりがちですが、
この時のダメダメ攻撃により
子供の潜在意識に『ダメ』が刷り込まれてしまうのです。
自己肯定感や価値観は親の影響が『大』である
親御さんが仕事等で忙しくお子さんとなかなか関わっている暇がないご家庭もあれば、常に親御さんがお子さんと密に関わっているというご家庭もあります。
しかし、
一緒にいる時間が長いかどうか
関わっている時間が長いかどうか
という問題ではなく
お子さんへの声の掛け方重要なのです。
ダメとか良いとかは親の価値観
親は色々と先回りをして、それが優しさだと思って
あれもダメ!これもダメ!とばかり言っていると、子供には
『あれもこれもしちゃダメなんだ…』
と無意識に刷り込まれていってしまいます。
先程も言いましたが、
子供の潜在意識の中に『ダメ』が入ってしまう。
それが
I am not OK(私はダメなんだ…)
に繋がってしまうのです。
ですので親としては、
『サポートする』
『危なくなった時に手を貸す』
くらいの方が良いということです。
自己肯定感は親の影響?自己肯定感が低い理由・まとめ
今回の
自己肯定感は親の影響なのか?
自己肯定感が低い本当に理由は何なのか?
について最後にまとめると下記のとおりです。
- 自己肯定感は親の影響が大
- 幼少期の親から子への『ダメダメ攻撃』が潜在的に刷り込まれて自己肯定感の低下につながる
- コミュニケーションは量より質
- 『ダメダメ』ではなく『見守り』作戦で I am OK(私は私で良いんだ)へと導く
次回は
人の価値観が、どう人の価値観に影響を与えるのか?
についてお話していきたいと思います。
本日もお読み頂きありがとうございました。